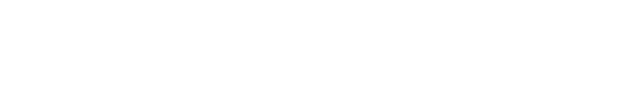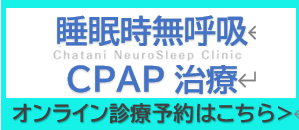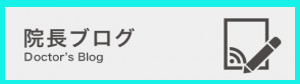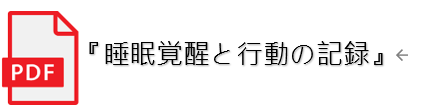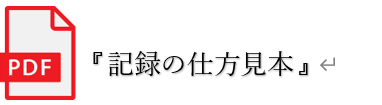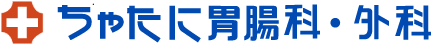第49回日本睡眠学会総会に参加して
 2025年6月28日~29日に広島大学霞キャンパスで行われた学会に参加してまいりました。
2025年6月28日~29日に広島大学霞キャンパスで行われた学会に参加してまいりました。
これまでは日程の関係でなかなか現地に行くことが難しかったのですが、今回は地元開催ということもあり両日とも参加できました。
色々と学びはありましたが、特に関西医科大学小児科の柳夲嘉時先生による、起立性調節障害の話が印象的でした。
起立性調節障害(Orthostatic Dysregulation:OD)という言葉は、世界では起立不耐症(Orthstatic Intrerance:OI)と呼ばれているそうです。
人間が立っている時、重力で血液が脚の方にひっぱられるわけですが、自律神経の働きで自動的に下肢の血管が締まることで頭への血流が保たれ失神しないように出来ています。
起立性調節障害の患者さんはその自律神経の働きが十分ではなく、朝に起きようとすると頭に血液が充分行かなくなることで倦怠感や頭痛を生じ、結果としてベッドから出られないという状態になってしまいます。雨の日や、台風、梅雨時が特にひどいようです。夜になると元気になります。
小学校高学年から増加し、中学生の10%に生じ半数が不登校になってしまうそうです。女子が多いのですが、月経があることが関係していると考えられています。
病態を簡単に説明するならば、思春期になって身体は大人になるものの神経の発達がそれに追いついていない状態で、いわば大人の身体を子供の神経が動かしているため、不十分な自律神経の働きにより症状がでてしまうとのことでした。従ってもっと成長して16-17歳頃になると症状が軽快していきます。
そういう訳で基本的には自律神経の働きの病気、つまり身体疾患であり、最近では循環器内科で診療されるようになってきたそうですが、ストレスや心の状態が影響していることがあるため歴史的には心療内科で診られてきました。
診断としては起立試験(ベッドに10分横になった時の血圧を測り、その後立ってもらって血圧が回復するまでの時間を計ったりどれくらい血圧が下がるかをみる)の結果を基に診断し、4つのサブタイプに分類されます。起立直後性低血圧が最多といわれています。
ここでとても興味深かったのは、起立性調節障害を人為的人工的に作る実験についての説明でした。宇宙飛行士はほとんど重力のない世界にいるためいわば寝たきりのような状態ですごしており、地球に帰還したときには自律神経の調節機構がうまく働かなくなり立位をとると失神してしまいます。先生が紹介された実験は、ラグビー部員をベッド上で10日間頭をおこさないようにして生活させると、起立性調節障害の診断基準を満たす状態になったというものでした。
これは、もともと起立性調節障害がない人でも、ストレスなどで休んで家でごろごろしすぎているといつのまにか起立性調節障害を発症してしまう可能性を示唆しています。こうなるとストレスで体調がわるいことと区別しにくく診断が難しくなりそうですね。
さて、起立性調節障害の治療としては、まず病態を本人と家族が知ることと、つづいて非薬物療法が行われます。具体的には1日20-30分の運動(散歩や自転車など下肢を動かす運動)、水分を1日2リットル摂る(1回200mlを8-10回に分ける)、塩分を1日10-12gとる(若者は少々塩分が多くても問題ないとのことです)、急に立ち上がらず30秒以上かけてゆっくり立つ、起床してあるくときは頭を前に下げたままで歩く、昼の12時までには起床して午後から活動する、午後は身体を横にしない、圧迫ソックスを履く、などの説明がありました。薬物療法もありますが、まずは非薬物療法を行わないと効きづらいそうです。改善するには年単位で時間がかかり、薬も効果がでるまで1-3ヶ月はかかるため、すぐに内服をやめてしまわないようにすることも重要とのことでした。
当院は睡眠クリニックのため、朝起きられないという若者が結構いらっしゃいます。基本的には朝目覚めているけれどもベッドから出られないのが起立性調節障害、朝になっても寝ているのが睡眠相後退症候群などの睡眠関連疾患と考えますが、両者の合併もありますし、起立性調節障害のために起きるのが遅くなった結果睡眠相が後退することだってあるため、今後も注意をしていこうとあらためて思いました。
最近の学会はオンデマンドで講演を見ることができるものが増えたため地方在住者としては助かるのですが、オンデマンド対象でない講演(この講演もそうでした)や現地にいかないと手に入らない情報もあるため、診療に影響が出すぎない範囲でなるべく参加しようと思いました。